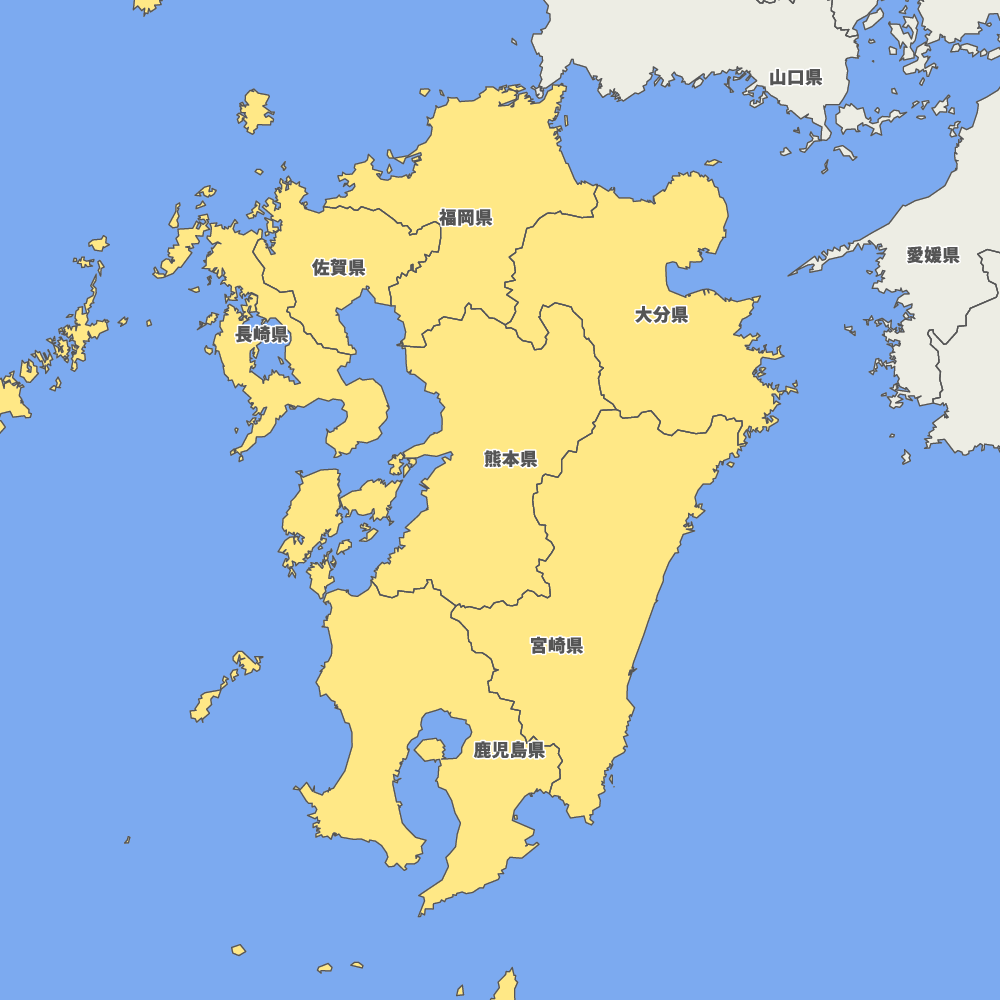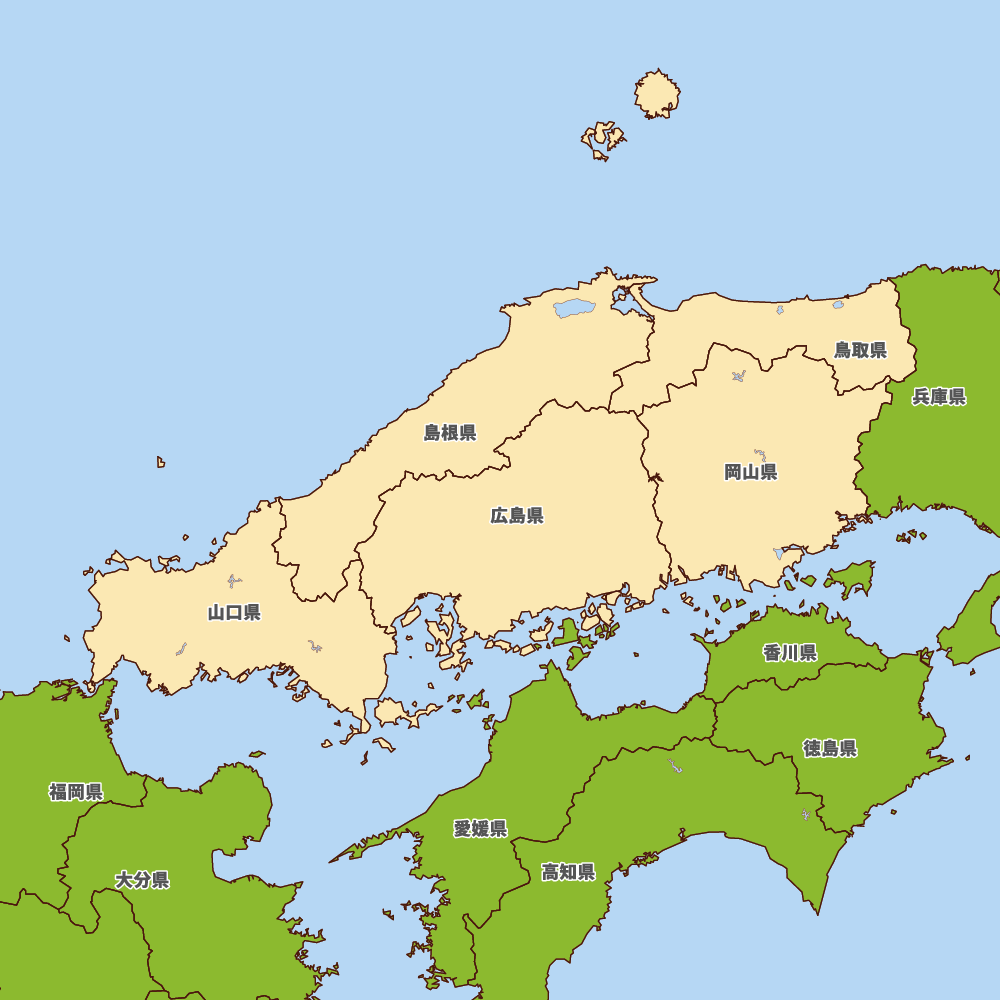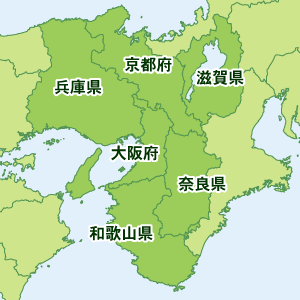【はじめに】
那覇空港に降り立った瞬間、空の色が違って見えました。
雲の合間から顔をのぞかせる陽光は、どこか柔らかく、でも確かに力強い。
頬をなでる風は、潮の匂いをふくみながら、遠い海の記憶を届けてくれるようでした。
沖縄――この言葉の響きには、いつも少しだけ郷愁が混じります。
初めて訪れるはずなのに、なぜか懐かしく、どこかで会ったことがあるような気がする。
そんな不思議な感覚を胸に、私は今回の旅をはじめました。
本州の喧騒から少し距離を置いて、自然の中に身をゆだねる時間。
真っ白な砂浜と、限りなく透明な海。赤瓦の屋根が連なる古い町並み。
そして、時を超えて語り継がれてきた島の記憶。
沖縄は、そのすべてをやさしく包み込むように、旅人に語りかけてきます。
この旅では、那覇から南部、そして中部・北部・離島へと足を延ばし、それぞれの土地が持つ表情に、ゆっくりと触れていきました。
喧騒の中にある静けさ、笑い声の奥にある祈り――沖縄という島の奥行きを、少しでも感じていただけたら幸いです。

【1】那覇から南部へ:歴史と祈りの風景を歩く
那覇市の国際通りは、にぎやかで、どこかエネルギーに満ちた場所。
観光客が行き交い、屋台からは沖縄そばの香り、雑貨店の前には琉球ガラスの鮮やかなきらめき。
ここは、旅の始まりにふさわしい“玄関口”です。
一歩路地に入れば、首里の町並みが静かに広がります。
かつての琉球王国の中心地「首里城」は、2019年の火災で多くを失いながらも、今もなお、多くの人々の記憶と祈りをつなぎとめている場所です。
再建中の現地を訪れたとき、赤瓦の向こうに広がる那覇の町を見下ろしながら、どこか神聖なものに触れたような気持ちになりました。

そして、南へと車を走らせると、風景は一変します。
海が近くなり、空はどこまでも広く、空気に混じる塩の匂いが濃くなってくるのです。
沖縄戦の記憶が刻まれた「ひめゆりの塔」や「平和祈念公園」。
ここでは観光という言葉がそぐわないほどに、静かで、重たい空気が流れていました。
ひとつひとつの名前が刻まれた石碑に手を合わせ、目を閉じると、遠いはずの歴史が急に自分のすぐそばにやってくる感覚に襲われました。
でも、その静けさの中にも、確かに希望があるのです。
公園を歩いていると、地元の小学生が修学旅行で訪れていて、真剣に資料に目を通している姿がありました。
語り継ぐということ、忘れないということ、それはこの島が何よりも大切にしている営みなのかもしれません。
そして南部の旅の締めくくりには、知念岬へ。
ここは、風が抜ける岬の上から、エメラルドグリーンの海を一望できる絶景の地。
眼下には久高島が静かに浮かび、海と空の境目がゆるやかに溶け合っていました。
あのとき感じたのは、言葉ではうまく言い表せない、ただただ“祈るような気持ち”だったのです。

【2】中部:文化と暮らしの交差点、読谷・北谷・うるまを巡る
沖縄の中部――そこには、観光地としてのにぎわいと、地元の暮らしの息づかいが心地よく混ざり合った、絶妙な“ちょうどよさ”がありました。
那覇から車で北へ約1時間。
まず訪れたのは読谷村(よみたんそん)。
ここは観光ガイドに派手には載っていないけれど、旅人の心をふっと解きほぐしてくれる、そんな場所です。
最初に立ち寄ったのは、静かな丘の上に佇む「座喜味城跡(ざきみじょうあと)」。
かつて琉球王国を守った城壁が、今もなお美しい曲線を描いて空にのびていました。
城跡に立ち、風に吹かれていると、不思議と過去と現在の境界線があいまいになります。
この石を積んだ人は、どんな空を見ていたのだろう。
そんな想像が、旅の時間をより深く、豊かなものにしてくれるのです。

読谷といえば、やちむん(沖縄の焼き物)の里としても知られています。
赤瓦の工房が点在する「やちむんの里」では、土の匂いと、ろくろの回る音が静かに流れていました。
職人さんの手のひらから生まれる器たちは、どれもぽってりとあたたかく、ひとつひとつ表情が違う。
それはまるで、沖縄そのもののように思えました。
そこから車を走らせ、北谷(ちゃたん)の美浜アメリカンビレッジへ。
ここは一転して、ポップでカラフル、どこか異国の香りが漂う街並みが広がっています。
海辺の遊歩道を歩けば、夕暮れどきの空がだんだんとオレンジから群青へと色を変え、遠くに広がる東シナ海が静かにきらめいていました。
ふと立ち寄ったカフェで飲んだ、パッションフルーツのソーダ。
キリリとした酸味と甘さが混じり合い、湿った空気の中で喉をスーッと抜けていきました。
店主は移住してきたという東京出身の男性。
「沖縄の人の時間の流れ方が好きなんです」と笑っていました。
そう、その言葉には、私自身も頷かずにはいられませんでした。

そして、うるま市へ。
ここには、なんとも不思議な“海中道路”という風景があります。
まるで海の上を車で走っているかのような、真っ直ぐな道。
両側には透き通った青が広がり、風が車体を軽く揺らしながら吹き抜けていきます。
この道の先にあるのは、浜比嘉島、伊計島、宮城島など、小さな離島たち。

どの島にも、それぞれの暮らしがあり、静かで、やさしい時間が流れています。
浜比嘉島では、古民家の軒先でゆんたく(沖縄方言でおしゃべり)をしていたおばあちゃんたちが、「今日は風が強いねぇ」と笑いながら手を振ってくれました。
その一言が、なぜか胸に沁みました。
言葉の意味よりも、そのまなざしや声のトーンの中に、あたたかい“受け入れ”のようなものが確かにあったのです。
こうして中部を巡る旅は、にぎやかさと静けさのあいだをゆらゆらと揺れながら、心の奥にゆっくりと沁み込んでいきました。
風景だけでなく、出会った人々の声や、道端に咲く花の色、夕焼けの匂いまでもが、旅の記憶として残っていくのを感じました。
【3】北部:やんばるの森と、海の青に抱かれて
沖縄本島の北部に広がる“やんばる(山原)”――それは、まるで島の“深呼吸”のような場所でした。
読谷からさらに車を北へと進め、名護の市街地を越えたあたりから、風景は徐々に“人の気配”から“自然の息吹”へと変わっていきます。
道はくねくねと曲がり、左右には深い緑。
目に入るものすべてがしっとりとした湿度を含み、森の中からは鳥のさえずりと虫の音、時おり木の実が落ちる音が混ざり合って響いてきます。
まず訪れたのは、国頭村(くにがみそん)にある「やんばる国立公園」。
広大な山の中に点在するトレッキングルートを歩きながら、私はふと立ち止まり、耳を澄ませました。
風が木々を揺らし、その隙間から日差しがこぼれ落ちてくる瞬間――その何気ない一瞬に、心がじんわりとあたたかくなるのです。
やんばるには、世界自然遺産にも登録された貴重な動植物が多く棲んでいます。
運がよければ、「ヤンバルクイナ」や「ノグチゲラ」といった固有種に出会えるかもしれません。
私は双眼鏡を手に歩いていましたが、姿を現してくれたのは、森の奥でピョンと跳ねるリュウキュウアカガエル。
それでも、何だか大きな宝物を見つけたような気持ちになりました。

次に向かったのは、東村にある「慶佐次(げさし)のマングローブ林」。
カヤックに乗って、水の上をゆっくりと滑るように進むと、マングローブの根が絡まり合う複雑な造形が目の前に広がります。
パドルを止めると、そこには静寂だけがありました。
耳を澄ませば、水面に魚が跳ねる音、どこかで鳥が羽ばたく音、そして自分の呼吸だけがゆっくりと重なっていく――自然と一体になるような、贅沢な時間でした。
やんばるの旅は、ただ自然を見るだけの旅ではありません。
その自然の中で、“自分”という存在と静かに向き合う旅でもありました。
夕暮れ時、私は本部町(もとぶちょう)にある「備瀬(びせ)のフクギ並木」へと向かいました。
ここは、まるで時が止まったかのような静かな集落。
フクギ(福木)という樹木が防風林として整然と植えられ、その間を縫うように石畳の小径が続いています。
レンタサイクルを借りてその並木道を進めば、木漏れ日が肩を優しく撫でてくれるような、不思議な安心感に包まれます。
近くの民家では、猫がひなたで丸くなり、縁側にはのんびりと三線の音色が流れていました。
観光地というより、そこは“誰かの暮らし”の風景。
その静けさに触れた時、「旅は特別なものだけじゃない」ということを、しみじみと思い出させてくれた気がします。

そして、旅の締めくくりとして選んだのは、「古宇利島(こうりじま)」。
本島と橋でつながったこの小さな島は、恋の島としても知られています。
全長約2kmの古宇利大橋を渡ると、目の前に広がるのは、夢のようなエメラルドグリーンの海。
まるで絵画のような景色に、何度も「本当にここは日本なのだろうか」と、心の中でつぶやいてしまいました。
海岸を歩き、波打ち際に腰をおろして空を見上げた時、やんばるでの旅の記憶が、まるでやさしい波のように胸に押し寄せてきました。
沖縄の北部――そこは、自然の美しさと、人の暮らしが調和した、心の奥深くに届く場所だったのです。

【4】離島編:青い海の彼方へ
沖縄本島の北部を満喫した後、次に向かうのは、沖縄の海を代表する美しい離島たちです。
那覇の賑やかな街を後にし、飛行機で石垣島へ。
南国の風が迎えてくれると、心が自然と解きほぐされていくような気がしました。
沖縄本島とはまた違う空気、そして、離島ならではの“ゆっくり”とした時間が流れる場所です。
最初に訪れたのは、石垣島。
空港を降りると、そこには目の前に広がる青い空と海が、心を引き込んでやまない。
石垣島は、その美しい海と白い砂浜で有名で、特に「川平湾(かわびらわん)」はその象徴的な風景として有名です。
川平湾の透明度の高い海を前に、私は思わず息を呑みました。
遠くの島々が水面に映るさまは、まるで絵画のようで、しばらくその場でただ見入ってしまったほどです。
川平湾では、グラスボートに乗って海底の世界を覗いてみました。
海中には、色とりどりの熱帯魚たちが泳ぎ回り、サンゴが生き生きと息づいています。
こんなにも澄んだ海は、他のどこにもないのではないかと感じました。

午後には、島の南部へと足を延ばし、あえて観光地として名の知られた場所から離れたところへ。
石垣島には、まるで秘境のように静かな場所がいくつもあります。
たとえば「玉取崎(たまどりざき)」という小さな岬から見える景色は、地元の人たちにとっても特別な場所だとか。
ここからは石垣島の大自然と、島々が織り成す美しい風景を一望できます。
次に訪れたのは、石垣島からさらに南に位置する宮古島です。
飛行機を降りると、石垣島とはまた違った風景が広がっています。
宮古島は、その名の通り“島”という言葉そのもののような場所で、どこまでも続く海と白い砂浜が心を解き放ってくれます。
特に有名なのは、「与那覇前浜(よなはまえはま)」。
広大なビーチに足を踏み入れると、透明な海と空がまるで一体化しているかのような感覚に包まれます。
宮古島の海は、色が何層にも重なり合い、そのグラデーションの美しさに言葉を失ってしまうほどです。
与那覇前浜でしばらく海を見つめていると、次第に心が洗われていくのを感じました。

また、宮古島には「東平安名岬(あがりへんなみさき)」という、自然の美しさと静けさを体感できる場所もあります。
ここからは、宮古島の海岸線とその先に浮かぶ小さな島々を見渡すことができ、息を呑むほどの壮大な景色が広がっています。
風に揺れる草の音、波の音。
普段の忙しさを忘れて、ただその瞬間に身を任せることができる場所でした。
宮古島から船でわずか10分ほどで渡れる竹富島。
ここは、沖縄の古き良き風景が色濃く残る場所です。
竹富島に着いた瞬間、そこはまるで時が止まったかのように感じられました。
島内は車の通行が制限されており、代わりにレンタルサイクルや、古き沖縄の赤瓦屋根が並ぶ小道を歩きながら、島を散策します。
島の中心には、まるで絵葉書のような風景が広がっています。
赤瓦の民家、白い砂の道、そしてその先に広がる海と空。

このシンプルな風景こそが、竹富島の魅力であり、何度訪れても心が穏やかに満たされる場所です。
歩いていると、ふと島の人々と目が合い、穏やかな笑顔を交わすことができるのも、この島ならではの暖かさです。
竹富島では、星空もまた特別です。
夜になると、空一面に広がる星々がそのまま島を包み込むかのような美しい景色が現れます。
星の輝きが、島の静けさをさらに引き立ててくれるのです。
【5】沖縄の離島の美しさに浸る
沖縄本島から、さらに南の離島にまで足を運ぶことができたこの旅。
そこには、どこか懐かしさを感じさせる風景と、地元の人々の温かいおもてなしがありました。
沖縄の離島は、それぞれが異なる魅力を持ちながらも、共通して“ゆっくり”とした時間が流れています。
都会の喧騒から離れて、ただ自然と向き合い、人々と触れ合い、心をリセットすることができる場所――それが、沖縄の離島の最大の魅力です。
これからも、沖縄の風景や文化、人々とのふれあいを通じて、心に残る旅を続けていきたいと思います。
次回は、沖縄の食と音楽、そして平和への祈りに触れる旅へと続きます。