【はじめに】
西日本のほぼ中央に広がる中国地方。
鳥取、島根、岡山、広島、山口――この五県から成る地には、にわかに語り尽くせぬほどの魅力が詰まっています。
海があり、山があり、神話が息づき、歴史が今もなおそっと脈打ち、そしてそこに暮らす人々のあたたかな暮らしがある。
その風景に包まれるたび、心の奥底から「ただいま」と呟きたくなるような、不思議な懐かしさが込み上げてきます。
今回の旅は、そんな中国地方を、少しゆっくりと、少し丁寧に巡ってみたいと思ったところから始まりました。
移動手段も、早さや効率を重視するのではなく、敢えて時間をかけて、その土地の空気を身体いっぱいに取り込むことを大切にしました。
特急列車からローカル線へ。時にはバスや渡し船、時には自転車や自分の足で。
旅の速度がゆっくりになるほどに、目に映る風景の輪郭が、よりやさしく、より鮮やかに感じられるのです。
道すがら、駅前のベンチで地元の方と交わした短い会話や、早朝の市場で見かけた魚屋の威勢の良い声、雨上がりの神社で聞いたしっとりとした木々の香り。
そうした小さな出来事の一つひとつが、まるで風のように私の旅路にそっと吹き込み、気づけば心の奥にまで染み渡っていました。
中国地方の旅には、大都市のような華やかさやにぎやかさは少ないかもしれません。
でも、その代わりに、人や自然が持っている“素のままの美しさ”が、息を潜めながらも確かにそこに存在していて、ふとした瞬間にこちらの心を優しく包んでくれます。
この旅では、まず鳥取の砂丘で見た風と光の揺らぎから始まり、島根では古の神々が宿る場所で静かな祈りに触れました。
岡山の町では、桃太郎伝説の残る中で人情に出会い、広島では過去と未来が交差する記憶の場に立ち尽くし、そして山口では、旅の終わりにふさわしいほどの、美しい海と夕陽に見送られました。
どの地にも、それぞれ異なる息づかいがあり、そこでしか得られない体験がありました。
そして何よりも、この旅を通じて感じたのは、「その土地の風景を見る」ということが、単に目で眺めるだけではなく、「心を通わせる」という行為でもあるのだということです。
風に揺れる草の音、ふいに香る花の匂い、見知らぬ人との挨拶。そのすべてが、旅人にしか出会えないかけがえのない瞬間です。
これから綴っていくのは、そんな小さな出会いと発見の積み重ね。
きっとあなたの中にも、ふと重なる景色があるかもしれません。
五つの県が織りなす、五つの色彩。
どうぞ、その風景に心を預けながら、ゆっくりと読み進めていただけたら幸いです。
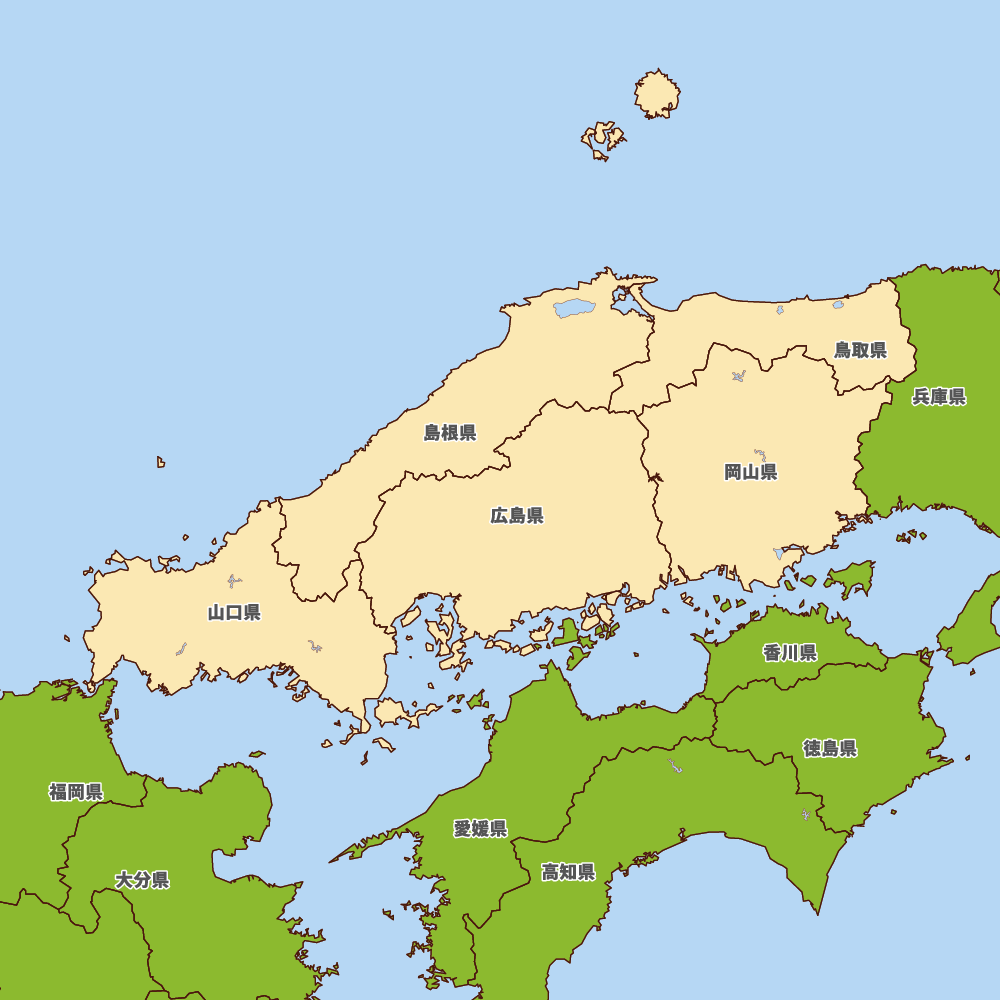
【1】鳥取:風と砂の詩が聞こえる場所
山陰の玄関口、鳥取。
全国で最も人口の少ない県と言われながらも、この地には、言葉にならないほどの“濃密な静けさ”が満ちています。
人の手が届きすぎないからこそ残るもの、風が語りかけてくるような景色、人の声がちゃんと心に届く距離感——そんな旅が、ここにはありました。
旅の始まりは鳥取駅。
朝のまだ静かなホームに降り立つと、凛とした空気が肌に触れ、背筋が自然と伸びるような感覚に包まれました。
駅前の通りには大きなビルも喧騒もなく、そこにはどこか昔懐かしい、ゆったりとした時間の流れがありました。
列車の音、信号の切り替わる音、それらが妙に心地よく響いてきます。
タクシーに乗り込み「砂丘までお願いします」と伝えると、年配の運転手さんがにっこりと「今日は風があるから、きっと砂が踊っとるで」と一言。
その言葉が妙に印象に残り、私は胸を少し高鳴らせながら窓の外を眺めました。
街並みが次第に田園へ、そして草地から広がる砂丘の前触れへと移ろっていく景色に、旅の実感がじわりと染み込んでいきます。
そして見えてきた、鳥取砂丘。まるで海のように広がる一面の砂。
誰もが思わず息を呑むほどのスケールです。
足を踏み入れると、サラサラとした細やかな粒が靴の隙間から入り込み、次第にその砂の柔らかさに身も心も解かれていくような感覚に。
陽射しが作る影と風が描く波模様は、まるで大地が自ら詩を紡いでいるかのようで、私はしばらく無言でその光景を眺めていました。
「馬の背」と呼ばれる砂丘の頂に登ると、そこには青い海がどこまでも広がっていました。
風が強く、髪が頬を打ち、コートの裾がばたつきます。それでも足を止めたくなるほど、美しい風景。
日本海の白波が、光をきらきらと反射させながら押し寄せてくる様子は、どこか心の深い部分を揺さぶってくるようでした。
隣で写真を撮っていたカップルが「風、すごいけど気持ちいいね」と笑い合っていて、その何気ない一言すら、この風景を物語る一節のように感じられました。

砂の美術館にも足を運びました。
展示テーマはその年ごとに異なり、今回は「南米」でした。
マチュピチュ、インカの神殿、サンバを踊る人々……すべてが砂で形作られているとは信じがたいほどの緻密さと迫力。
館内を歩いていると、ふと「この砂も、あの砂丘の一部なんだよな」と思い、不思議な感動に包まれました。
儚くも力強く、ただの“粒”がここまでの芸術になる。
その対比が、旅人の心に深く刻まれます。
午後は「白兎神社」へ。
神話「因幡の白うさぎ」の舞台として知られるこの場所は、小さな神社でありながら、訪れた人の心に優しく寄り添うような、あたたかさがありました。
参道の両脇には小さなうさぎの石像が並び、その一つひとつに人々が願いを込めた跡が見て取れました。
境内で出会った親子が、うさぎの像に小さな手を合わせて「また元気に来ようね」と囁く声を聞いて、胸が少し熱くなりました。
旅先でふと目にする、こんな小さな祈りの場面ほど、忘れがたいものはないのかもしれません。

夜は鳥取駅近くの小さな居酒屋へ。
灯りのともる暖簾をくぐると、木のぬくもりに包まれたカウンター席が迎えてくれました。
地元の松葉ガニ、白イカの刺身、砂丘らっきょうの浅漬け。
どれも素朴ながら、素材の味が活きていて、心もお腹もじんわりと満たされていきます。
店のご主人が「このカニは、今朝、賀露港で揚がったばっかり」と笑顔で教えてくれたとき、その一言が旅の味を何倍にも豊かにしてくれるのだと、改めて感じました。
帰り道、空を見上げると、びっくりするほどの星空。
都会では見えないような無数の星たちが、音もなく瞬いています。
こんなにもたくさんの星が、毎晩空に浮かんでいたのかと、しばらくその場から動けませんでした。
冷たい風に吹かれながら、ただ立ち尽くしていたあの時間は、今でも私の中で鮮やかに残っています。
鳥取は、静かな場所です。
でもその静けさは、決して寂しさではなく、むしろ人の心をあたたかく包むような優しさに満ちています。
喧騒のない町並み、ゆっくりと進む時間、やわらかな人々の笑顔。
きっとまた、ふとした瞬間にこの風景を思い出すだろうな——そう確信しながら、私は次の目的地・島根へと向かう列車に乗り込みました。
【2】島根:神話と暮らしが交わるところ
鳥取から西へと向かう列車の車窓には、ゆるやかな丘と田園風景が広がり、時折、ちらりと見える日本海がその旅の輪郭を淡く彩ってくれます。
空はどこまでも広く、雲はまるで浮かんでいるというよりも、空に溶け込んでいるかのよう。
そうして、静かな時間を経て辿り着いたのが、島根県。
出雲の国として名高いこの地には、どこか現実とは少し違った“時間の層”が流れているように感じられました。
まず向かったのは、やはり「出雲大社」。
日本最古級の神社のひとつであり、縁結びの神様としても知られる大国主大神を祀る場所です。
長い参道を歩くたびに、砂利の音が心の内を整えてくれるようで、不思議と姿勢も正されていくのを感じました。
境内に入ると、圧倒的な存在感を放つ御本殿の大屋根。
その前で自然と手を合わせた瞬間、目には見えないはずの「何か」に、そっと包まれたような感覚がありました。
出雲大社での参拝は、通常の神社とは異なり「二礼四拍手一礼」。
その拍手の音が、風に乗って木立の間へ吸い込まれていくようでした。
多くの人が訪れていながらも、この場所には決して喧騒はなく、むしろ人の祈りが互いに溶け合うことで、静けさが深まっていくような、そんな空気がありました。
神楽殿にかかる大注連縄(おおしめなわ)は、まるで空から吊るされた太い命綱のようにも見え、見上げているだけで心が引き締まります。
そこに流れているのは、きっと神話ではなく、確かに“今ここ”にある人々の信仰の重なりなのでしょう。

神社の外に出ると、出雲そばのお店が並ぶ通りが現れました。
三段重ねの割子そばに、薬味とつゆをかけながらいただくこの郷土料理は、見た目の可愛らしさとは裏腹に、しっかりとした風味とそばの香りに満ちていて、旅の疲れもすっとほぐれていくようでした。
隣の席にいた地元のおばあさんが「出雲は、食べ物も、人の縁も、どれも“よう噛みしめる”ところなんよ」と話しかけてくださり、その言葉が妙に心に残ったものです。
午後には、「日御碕灯台」へ。
岬に立つ真っ白な灯台は、日本一の高さを誇り、海から吹き上げる風と、荒々しくも美しい岩場の景色に、思わず時間を忘れました。
目の前に広がるのは、神々の歩いたという出雲の海。
光の差し込み方が一瞬一瞬変わるたびに、同じ海でも全く違う表情を見せてくれます。
眼下に広がる碧い海と、打ち寄せる白波、その向こうに霞む水平線を見ていると、「人間の営みって、ほんのひとひらなんだな」と、なんとも言えない気持ちになりました。
そしてもう一つ、どうしても訪れたかった場所がありました。
それは「石見銀山」。
かつて世界中に名を轟かせたこの鉱山は、今ではその役目を終え、静かな山里として静かに息づいています。
世界遺産にも登録されているこの地は、ただの観光地ではありません。
石畳の坂道、古い町屋、手入れの行き届いた庭先――そこには、時を超えて続く暮らしの温度があります。

「銀山公園」で出会った案内ボランティアの男性が、「この町はな、昔から“儲けた金より、残した縁”が大事って言われとったんよ」と笑いながら教えてくれました。
その言葉が、出雲大社で感じた「つながり」ともどこか通じ合っていて、私は島根という土地の奥深さに静かに感動を覚えました。
日が暮れかけた頃、「宍道湖(しんじこ)」のほとりへ。
夕日が湖面をゆっくり染めていくさまは、あまりに静かで、あまりに美しくて、ただただ見惚れてしまいました。
湖畔には釣りをする親子、ベンチに並ぶ老夫婦、そしてひとりぼんやりと佇む旅人――それぞれが自分の“静かな時間”を過ごしていて、湖はそのすべてを、ただやさしく受け入れてくれていました。
島根の旅は、派手な出来事やきらびやかな景色よりも、心の奥で確かに灯る“言葉にならない想い”が積み重なっていくような時間でした。
祈ること、待つこと、つながること。
島根には、それらを何気ない日常の中に大切に残している“静かな強さ”があるように思います。
次は、山の都・広島へ。
列車がゆっくりと西へと進む中、私は出雲の海と宍道湖の静けさを、心の奥にそっとしまいこみました。
【3】広島:祈りと再生が交差する都市
列車は島根のしっとりとした風景を後にし、再び西へ。
中国山地を越えた先、広島の街が徐々にその姿を現しました。
駅に降り立った瞬間、ふわりと漂ってきたのは、お好み焼きの香ばしい匂い。そして、にぎやかな電車の音と人々の声。
そこには「日常」の手触りがしっかりと根を張っていて、どこか懐かしさすら覚えます。
広島といえば、やはりまず訪れるべきは「平和記念公園」。
原爆ドームの前に立ったとき、その静けさは胸にずしりと響きました。
骨組みだけが残された建物の輪郭は、言葉を越えた重みを持ち、ただ黙ってそこに立ち尽くすことしかできませんでした。
園内を歩くと、子どもたちが折った千羽鶴が色とりどりに風に揺れ、広島の空を優しく彩っていました。
慰霊碑の前でそっと目を閉じたとき、都市としての再生と、個人の祈りが交差する場所に自分が立っているのだと、深く実感したのです。
原爆資料館では、焼け焦げた衣服や瓦、無数の手紙や写真が展示されていて、一歩一歩が胸に迫ってきました。
戦争というものの愚かさと、人間の心の深さ――それらを目の当たりにしながら、「記憶すること」の大切さをひしひしと感じました。
けれど、広島は「悲しみ」だけの街ではありません。

平和記念公園を後にして、歩いて向かった先は「本通り商店街」。
活気あるアーケードには、学生たちの笑い声や、買い物を楽しむ人々の姿。
人々が普通に笑い、暮らしているこの光景こそが、広島という街の“答え”なのだと思えました。
そして、広島名物といえば“お好み焼き”。
地元の人にすすめられて、小さな路地裏にある老舗の一軒へ。
鉄板の前に座り、焼き上がる音を聞きながらビールを一杯。
キャベツたっぷりの層にそばが敷かれ、甘辛いソースがじゅうっと香ばしく焼けたその味は、どこまでも温かく、そして懐かしい。
隣の常連さんが「広島焼きって言わんといてや、広島では“お好み焼き”やけぇ」と笑って話しかけてくれたのも、土地の人の気質を感じる素敵な一幕でした。
次の日は、世界遺産「宮島」へ。
フェリーに揺られながら見えてきた厳島神社の大鳥居は、思わず息をのむほどの美しさ。
ちょうど潮が引いていた時間帯だったので、歩いて鳥居の足元まで行くことができました。
海と空の境界が淡く溶ける中、そっと手を合わせていると、旅に出たことそのものに感謝したくなるような、不思議な心持ちに包まれました。
宮島の町並みもまた風情があり、木造の建物が並ぶ通りには、もみじ饅頭や焼き牡蠣のお店が立ち並んでいます。
熱々の牡蠣を頬張ったときのジューシーな海の旨味は、思わず声が漏れるほど。
鹿がのんびり歩く姿を眺めながら、商店街をぶらりと歩いていると、時間がゆるやかに流れていることに気づかされました。

その後、宮島ロープウェーに乗って弥山(みせん)へ。
標高535メートルの山頂から見下ろす瀬戸内海の多島美は、まるで墨絵のような繊細さと奥行きを持っていて、しばし言葉を失うほどの絶景でした。
空気は澄み、鳥の声だけが響く世界。
自然と静かに向き合うことで、自分自身の“芯”のようなものを探しているような、そんな気持ちになったのです。
広島は、確かに過去に深い傷を負った街です。
でもそれ以上に、前を向いて「生きること」にまっすぐな場所でもあります。
人々の笑顔の中に、料理の湯気の中に、復興の時間が静かに、確かに宿っている――そんなことを、旅を通して学んだ気がします。
次なる目的地は、山口。
列車に揺られながら、瀬戸内の光が車窓に反射するたびに、広島という街が胸の中で少しずつ、でも確かに、私の“人生の風景”になっていくのを感じていました。
